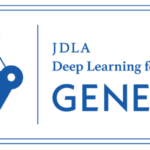はじめに
この記事は、G検定合格を目指すための実践的な問題集「100本ノック」の第一弾です。 以前の【G検定完全攻略】記事で解説した通り、合格の鍵は、自らの「苦手分野」を特定し、そこを徹底的に潰すことにあります。
この問題集を活用し、自身の理解度を測ってみてください。 第一回目は、試験の土台となる「AIの歴史」と「法律・倫理」に関する20問です。
それでは、始めましょう。
関連記事
-

-
G検定
1. 試験結果の概要 受験者数: 7,927名 合格者数: 6,051名 合格率: 約76.3% SNS上では「過去一番で難化した」との声が多数見られたが、合格率は過去の試験とほぼ同水準で推移した。こ ...
-

-
G検定
はじめに この記事は、G検定合格を目指すための実践的な問題集「100本ノック」の第一弾です。 以前の【G検定完全攻略】記事で解説した通り、合格の鍵は、自らの「苦手分野」を特定し、そこを徹底的に潰すこと ...
-

-
G検定
はじめに この記事は、G検定合格を目指すための実践的な問題集「100本ノック」の第二弾です。 第一弾の「AIの歴史と法律・倫理編」に続き、今回は、G検定の試験範囲の中核をなす「機械学習の基礎と、その主 ...
-

-
G検定
はじめに この記事はG検定合格を目指すための実践的な問題集「100本ノック」の第三弾です。 第二弾の「機械学習の基礎と主要な手法編」に続き、今回は第三次AIブームの中核技術である「ディープラーニングの ...
-

-
G検定
はじめに この記事はG検定合格を目指すための実践的な問題集「100本ノック」の第四弾です。 第三弾の「ディープラーニングの基礎と主要な手法編」に続き、今回は、AI技術が、現実社会で、どのように活用され ...
-

-
G検定
はじめに この記事はG検定合格を目指すための実践的な問題集「100本ノック」の最終回です。 今回はこれまでの分野を横断する「総合問題」として、あなたの知識が本当に定着しているかを確認するための20問で ...
問題1
1956年に開催され、「人工知能(Artificial Intelligence)」という言葉が初めて公の場で使われた、歴史的に重要な会議の名称として、最も適切なものを一つ選べ。
A. メイシー会議
B. ダートマス会議
C. ソルベイ会議
D. ブレトン・ウッズ会議
クリックして下さい
正解: B
解説: ダートマス会議は、1956年にアメリカのダートマス大学で開催された研究集会です。ジョン・マッカーシー、マービン・ミンスキー、クロード・シャノンといった研究者が集まり、この会議で「人工知能(AI)」という学術分野が正式に命名され、誕生しました。
問題2
コンピュータ科学の父とも呼ばれ、第二次世界大戦中にはドイツ軍の暗号「エニグマ」の解読に貢献し、機械が人間のように「思考」できるかを問う「チューリング・テスト」を提唱した人物として、最も適切なものを一つ選べ。
A. アラン・チューリング
B. ジョン・フォン・ノイマン
C. ノーバート・ウィーナー
D. ジェフリー・ヒントン
クリックして下さい
正解: A
解説: アラン・チューリングは、コンピュータの基礎理論を築いたイギリスの数学者です。彼が提唱した「チューリング・テスト」は、機械の知能を測るための思考実験として、今なおAIの哲学的な議論において重要な位置を占めています。
問題3
1950年代から1960年代にかけて起きた「第一次AIブーム」において、主流であった研究アプローチは何か。最も適切なものを一つ選べ。
A. ニューラルネットワークと深層学習
B. エキスパートシステムと知識表現
C. 探索と推論による問題解決
D. 大規模言語モデルと生成AI
クリックして下さい
正解: C
解説: 第一次AIブームでは、コンピュータに「ルール」と「ゴール」を与え、その間を論理的に探索・推論させることで、特定のパズルやゲームを解く、というアプローチが主流でした。これを「探索と推論」と呼びます。
問題4
第一次AIブームが終焉を迎えた「AI冬の時代」が訪れた主な原因として、最も適切でないものを一つ選べ。
A. 現実世界の複雑な問題には、ルールベースのアプローチが通用しなかったこと
B. コンピュータの計算能力が、研究者の理論に追いついていなかったこと
C. AIが人間の知能を超える「シンギュラリティ」への社会的な恐怖が高まったこと
D. トイ・プロブレム(おもちゃの問題)しか解けず、実用化への期待が裏切られたこと
クリックして下さい
正解: C
解説: 「シンギュラリティ」という概念が広く議論されるようになったのは、主に21世紀に入ってからです。第一次AIブームの終焉(1970年代)の主な原因は、AIが特定の問題しか解けず、現実世界の曖昧で複雑な課題に対応できなかったことや、当時のコンピュータの性能限界でした。
問題5
1980年代の「第二次AIブーム」を牽引した技術の中心的な概念として、最も適切なものを一つ選べ。
A. 探索と推論
B. エキスパートシステム
C. 機械学習
D. 強化学習
クリックして下さい
正解: B
解説: 第二次AIブームの中心は「エキスパートシステム」でした。これは、特定の分野の専門家(エキスパート)が持つ知識を「知識ベース」としてコンピュータに入力し、その知識に基づいて推論を行うことで、専門家のように振る舞うシステムのことです。
問題6
2006年以降の「第三次AIブーム」の火付け役となった、AI研究における画期的な技術は何か。最も適切なものを一つ選べ。
A. エキスパートシステム
B. ディープラーニング(深層学習)
C. 遺伝的アルゴリズム
D. サポートベクターマシン
クリックして下さい
正解: B
解説: 第三次AIブームは、ジェフリー・ヒントンらが提唱した「ディープラーニング(深層学習)」によって引き起こされました。人間の脳神経を模した多層のニューラルネットワークを用いることで、AIが自らデータの特徴量を学習することが可能になり、画像認識や音声認識の精度が飛躍的に向上しました。
問題7
個人情報保護法において、特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日など)のことを何と呼ぶか。最も適切なものを一つ選べ。
A. 要配慮個人情報
B. 仮名加工情報
C. 個人識別符号
D. 個人情報
クリックして下さい
正解: D
解説: 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できるものを指します。
問題8
個人情報保護法において、本人の人種、信条、社会的身分、病歴など、不当な差別や偏見が生じないように、特に配慮を要するものとして定められている情報を何と呼ぶか。
A. 個人情報
B. 要配慮個人情報
C. 匿名加工情報
D. 個人関連情報
クリックして下さい
正解: B
解説: 「要配慮個人情報」は、その名の通り、取り扱いに特に配慮が必要な、機微な個人情報のことです。本人の同意なく、この情報を取得することは原則として禁止されています。
問題9
EU(欧州連合)で施行されている、個人データ保護に関する包括的な規則の名称として、最も適切なものを一つ選べ。
A. CCPA (カリフォルニア州消費者プライバシー法)
B. APPI (個人情報保護法)
C. GDPR (一般データ保護規則)
D. プライバシー・シールド
クリックして下さい
正解: C
解説: 「GDPR(General Data Protection Regulation)」は、EU域内の個人のデータ保護を強化し、統一するための規則です。違反した企業には、全世界の売上の数%という、巨額の制裁金が科される可能性があります。
問題10
著作権法に関する記述として、最も適切なものを一つ選べ。
A. AIが自動生成したイラストや文章には、人間の著作物と同様の著作権が自動的に発生する。
B. AIの学習データとして、著作権で保護された画像や文章を、著作権者の許諾なく利用することは、常に違法である。
C. 著作権は、アイデアや作風そのものを保護するものではなく、具体的な「表現」を保護するものである。
D. 著作権は、登録しなければ発生しない。
クリックして下さい
正解: C
解説: 日本の著作権法は、具体的な「表現」を保護するものであり、アイデアや画風、文体といった抽象的な概念は保護の対象外です。また、AI生成物の著作権の有無や、AIの学習データの利用については、現在も議論が続いている領域であり、AやBは現時点では明確に「正しい」とは言えません。Dは誤りで、著作権は創作した時点で自動的に発生します(無方式主義)。
問題11
AIが、学習データに含まれる偏見や差別を学習してしまい、特定の属性を持つ人々に対して、不利益な判断を下してしまう問題のことを何と呼ぶか。
A. アカウンタビリティ
B. アルゴリズム・バイアス
C. シンギュラリティ
D. ブラックボックス問題
クリックして下さい
正解: B
解説: 「アルゴリズム・バイアス」とは、AIが、過去のデータに含まれる社会的な偏見(例:特定の性別や人種が、特定の職種に就きにくい、など)を学習し、それを再生産・増幅してしまう問題のことです。
問題12
ディープラーニングのように、AIの判断根拠が、あまりにも複雑で、人間には理解できない状態になってしまう問題のことを何と呼ぶか。
A. フレーム問題
B. シンボルグラウンディング問題
C. ブラックボックス問題
D. チューリング・テスト
クリックして下さい
正解: C
解説: 「ブラックボックス問題」とは、AIがなぜその結論に至ったのか、その判断プロセスを人間が説明・解釈できない問題です。特に、自動運転や医療診断など、判断の根拠が重要となる分野で、大きな課題となっています。
問題13
AIの判断プロセスを、人間が理解・解釈できるようにするための技術や考え方の総称として、最も適切なものを一つ選べ。
A. XAI(説明可能なAI)
B. AGI(汎用人工知能)
C. ELSI(倫理的・法的・社会的課題)
D. アライメント
クリックして下さい
正解: A
解説: 「XAI(Explainable AI)」は、ブラックボックス問題を解決し、AIの判断の透明性と信頼性を確保するための、重要な研究分野です。
問題14
自動運転車が、事故を避けられない状況で、「歩行者一人を犠牲にする」か「乗員一人を犠牲にする」か、といった倫理的なジレンマを問う思考実験として、最も有名なものを一つ選べ。
A. 中国の部屋
B. トロッコ問題
C. 囚人のジレンマ
D. テセウスの船
クリックして下さい
正解: B
解説: 「トロッコ問題」は、功利主義と義務論の対立を示す、倫理学の有名な思考実験です。AIに、どのような倫理的判断をプログラムすべきか、という文脈で、頻繁に引用されます。
問題15
AIが、自らより賢いAIを、再帰的に作り出すことで、人間の知性を、遥かに超える「技術的特異点」。その概念を何と呼ぶか。
A. シンギュラリティ
B. サイバネティクス
C. トランスヒューマニズム
D. ブロックチェーン
クリックして下さい
正解: A
解説: 「シンギュラリティ(技術的特異点)」は、レイ・カーツワイルらが提唱した、未来予測の概念です。AIが、人間の知能を、超越する時点、あるいは、それによって引き起こされる、予測不能な社会の変化を指します。
問題16
AIが、開発者や、運用者の意図や、価値観から外れず、人類にとって、有益な形で、振る舞うように、設計・調整することの重要性を指す言葉として、最も適切なものを一つ選べ。
A. アノテーション
B. アライメント
C. アジャイル
D. アバター
クリックして下さい
正解: B
解説: 「アライメント(Alignment)」は、AIの目標と、人間の価値観を、一致させる、という、AI倫理における、中心的な課題の一つです。
問題17
AI倫理の、基本原則に関する議論において、AIが、人間に危害を加えてはならない、という原則を何と呼ぶか。
A. 公平性の原則
B. 透明性の原則
C. 無危害の原則
D. 責任の原則
クリックして下さい
正解: C
解説: 「無危害の原則(Non-maleficence)」は、AIが、物理的、精神的、経済的な危害を、人間に与えるべきではない、という、AI倫理の、基本的な考え方の一つです。
問題18
AIを含む、科学技術の発展が、もたらす、倫理的・法的・社会的な課題。その総称として、最も適切なものを一つ選べ。
A. SDGs
B. DX
C. ELSI
D. Society 5.0
クリックして下さい
正解: C
解説: 「ELSI(Ethical, Legal, and Social Issues)」は、生命科学や、情報技術などの、先端科学技術に、伴って生じる、倫理的、法的、社会的な、諸課題を、包括的に指す言葉です。
問題19
AIに、特定のタスクを、学習させるために、大量のデータに、人間が、意味のある情報(タグ)を、付与していく作業のことを、何と呼ぶか。
A. データマイニング
B. アノテーション
C. クラスタリング
D. Webスクレイピング
クリックして下さい
正解: B
解説: 「アノテーション」は、AI、特に、教師あり学習モデルの、性能を、左右する、極めて重要な、前処理作業です。例えば、画像データに「犬」「猫」といった、タグを付ける作業が、これに当たります。
問題20
第一次AIブームから、第二次AIブームの間に訪れた、AI研究の、停滞期。これを、一般的に、何と呼ぶか。
A. AIサマー
B. AIフォール
C. AIウィンター
D. AIスプリング
クリックして下さい
正解: C
解説: 「AI冬の時代(AI Winter)」は、AIへの、過剰な期待が、裏切られ、研究資金が、途絶え、研究全体が、停滞した、1970年代中頃から、1980年代初頭、および、1980年代末から、1990年代初頭の、時期を指します。