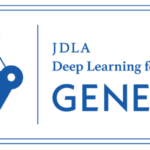1. 試験結果の概要
- 受験者数: 7,927名
- 合格者数: 6,051名
- 合格率: 約76.3%
SNS上では「過去一番で難化した」との声が多数見られたが、合格率は過去の試験とほぼ同水準で推移した。これは、試験が絶対評価ではなく「上位約75%を合格させる相対評価」である可能性を示唆している。
2. 出題傾向の変化
- 問題数の変更: 従来から160問へと減少した。
- 出題分野: ディープラーニングの概要・要素技術や、法律・倫理分野に重点が置かれる傾向は、過去の試験から継続している。
- 問題の質的変化:
- 試験範囲そのものの拡大というより、設問の表現や問い方に「クセ」が強くなった印象。特に、AIの社会実装に関する問題では、解釈が分かれるような曖昧な表現が増加し、確信を持って解答するのが難しい問題が見られた。
- 問題の二極化: 知識さえあれば即答できる簡単な問題と、長文で読解と思考を要する難しい問題の二極化が、より鮮明になった。特に試験序盤に難問が集中し、中盤から終盤にかけて簡単な問題が増える傾向が見られた。
3. 具体的な対策と戦略
上記の傾向分析から、今後のG検定に合格するためには、以下の戦略が有効であると考えられる。
基本戦略:満点を目指すな。「落ちない」ための勉強を徹底せよ
合格率が安定している以上、この試験の本質は「下位25%に入らないこと」である。奇問・難問は他の受験者も解けない可能性が高いため、固執する必要はない。それよりも「多くの受験者が正解するであろう基本的な問題を、絶対に落とさない」という守りの姿勢が重要となる。
インプット戦略
- 暗記ベースの継続: 試験の本質は、依然として知識の暗記が中心である。実務で使うかどうかは別問題として、英単語のように淡々と用語を頭に叩き込む作業は不可欠。
- 公式テキストの活用: 誤字が多いなど評判は芳しくないが、テキストからそのまま出題される問題も存在するため、一度は目を通しておくべき。「辞書」として活用するのが最も効率的である。
- 用語の別表記への対応: 「L1正則化=LASSO正則化」のように、同じ意味を持つ別の用語で問われるケースに備える必要がある。全てを暗記する必要はなく、試験中にすぐに参照できる自分だけのメモ(カンペ)を用意しておくのが現実的だ。
- ネットワーク知識の重点学習: 「LeNet」「AlexNet」「ResNet」など、紛らわしいネットワークの名称と、それぞれの特徴や技術的な変遷(ILSVRCの歴史と関連付けて)は、執拗に問われるため、重点的に学習する必要がある。これも、一覧メモを手元に置いておく戦略が有効。
アウトプット戦略
- 「なぜ」の理解: 単なる用語暗記から一歩進み、「なぜその処理をするのか」という目的や背景を理解することが、応用問題への対応力を高める。例えば、データ拡張の手法が、どのような課題を解決するためにあるのかを、自分の言葉で説明できるようにしておく。
- 時間配分のシミュレーション: 序盤の難問で心を折られないよう、模擬試験を通じて「2時間160問」のペース配分を、身体に覚え込ませることが必須。分からない問題は、迷わず飛ばす勇気が求められる。
- 合理的思考の活用: 中には、専門知識がなくとも、その場で合理的に考えれば解ける問題も存在する。「AICとBICの両方を使うのは良くない、は本当か?」→「いや、複数の指標で検討するのは、むしろ普通だろう」といった、冷静な思考を維持することが重要。
問題集リンク
G検定は、単なる暗記テストから、情報処理能力、時間管理能力、そして精神的な強さが問われる、より戦略的な試験へと進化している。 しかし、その本質が「上位75%に入ること」である限り、恐れる必要はない。
上記の対策を参考に、基本的な知識を確実に抑え、以下の問題集でアウトプットを繰り返せば、合格は決して難しい目標ではない。