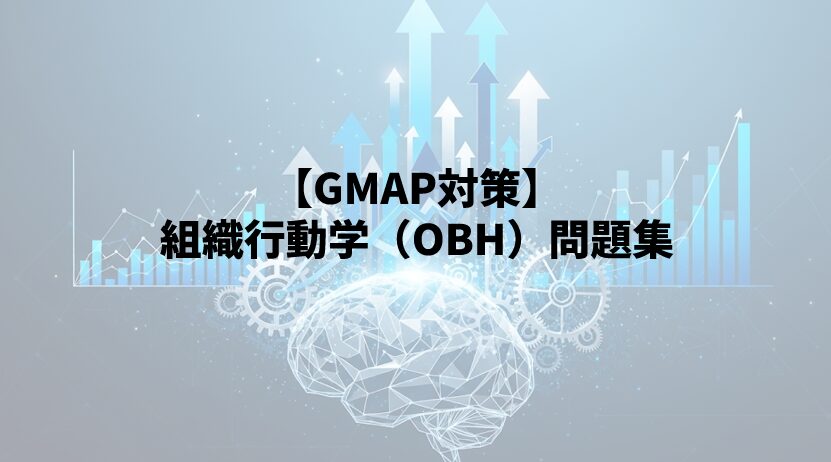
【第1問】リーダーシップとマネジメント
リーダーシップとマネジメントに関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
A. リーダーシップは、ビジョンを示し変革を促す「方向づけ」に関わり、マネジメントは計画を立て秩序をもたらす「管理」に関わる。
B. VUCAと呼ばれる変化の激しい時代においては、両者の能力を状況に応じて使い分けることがマネージャーに求められる。
C. ジョン・コッターによれば、強力なリーダーシップがあれば、マネジメント能力は必要ないとされる。
D. マネジメントが欠如したリーダーシップは組織を混乱に陥らせる危険性があり、両者は相互補完的な関係にある。
【第2問】エンパワーメント
部下に権限を委譲し、その能力を最大限に引き出す「エンパワーメント」を実践する上での留意点として、最も適切なものを一つ選べ。
A. 部下の能力レベルに関わらず、全ての業務を平等に委譲するべきである。 B. 権限を委譲した後は、部下の自律性を尊重し、進捗状況の確認やサポートは一切行わない。 C. 部下が自律的に判断できるよう、企業のビジョンや目標、行動規範を明確に共有しておくことが重要である。 D. エンパワーメントとは、上司の責任を部下に転嫁することと同義である。
【第3問】パワー
フレンチとレイヴンが分類した、人が他者に影響を及ぼす源泉となる5つの「パワー」のうち、個人の専門的な知識やスキルに対する周囲からの信頼に基づくパワーを何と呼ぶか。
A. 強制力
B. 報酬力
C. 同一視力(参照力)
D. 専門力
【第4問】モチベーションとインセンティブ
ダグラス・マクレガーが提唱した「X理論・Y理論」に関する記述として、正しいものを一つ選べ。
A. X理論は「人間は本来、仕事が好きで、自ら進んで責任を取ろうとする」という人間観に基づいている。
B. Y理論は「人間は本来、怠け者で、命令されなければ働かない」という人間観に基づいている。
C. Y理論的な人間観に立つマネジメントでは、従業員の自己実現欲求を満たすようなアプローチが有効とされる。
D. 現代のマネジメントでは、X理論に基づいた「アメとムチ」による管理が主流となっている。
【第5問】集団のメカニズム
集団浅慮(グループシンク)が発生しやすくなる条件として、当てはまらないものを一つ選べ。
A. 集団の凝集性が非常に高い。
B. 外部からの情報や意見に対して、組織が閉鎖的である。
C. メンバーの経歴や価値観が非常に多様である。
D. 強いリーダーシップを持つ人物が、早い段階で自分の意見を表明する。
【第6問】チーム・マネジメント
効果的なチームを構築するための要件として、最も適切でないものを一つ選べ。
A. チームの目標が明確であり、メンバー間で共有されている。
B. 各メンバーの役割と責任が明確に定義されている。
C. メンバー同士が率直に意見を交わせる、心理的安全性の高い環境がある。
D. チーム内の対立(コンフリクト)を避けるため、メンバーは同質的な専門性を持つ人材で構成するべきである。
【第7問】コミュニケーション
コミュニケーションのプロセスにおいて、送り手が伝えたい内容を言葉や表情、ジェスチャーなどの記号に変換するプロセスを何と呼ぶか。
A. 記号化(エンコーディング)
B. 伝達(チャネル)
C. 解読(デコーディング)
D. フィードバック
【第8問】コンフリクト
組織内のコンフリクト(対立)への対処法のうち、自分と相手、双方の満足度を最大化することを目指す、最も理想的とされるアプローチはどれか。
A. 競争(強制)
B. 回避
C. 妥協
D. 協調(協力)
【第9問】変革のマネジメント
クルト・レヴィンが提唱した、組織変革を成功に導くための3段階のプロセスモデルとして、正しい順番のものを選べ。
A. ①変革 → ②解凍 → ③再凍結
B. ①解凍 → ②再凍結 → ③変革
C. ①解凍 → ②変革 → ③再凍結
D. ①再凍結 → ②解凍 → ③変革
【第10問】組織学習
クリス・アージリスが提唱した組織学習のレベルに関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
A. シングルループ学習: 既存の行動規範や目標の枠組みの中で、行動の誤りを修正しようとする学習。
B. ダブルループ学習: 行動の誤りを修正するだけでなく、その背景にある行動規範や目標そのものにまで踏み込んで見直そうとする学習。
C. シングルループ学習は「適応的学習」、ダブルループ学習は「創造的学習」とも呼ばれる。
D. 多くの組織では、既存の価値観を疑うダブルループ学習よりも、シングルループ学習の方が容易に行われる。
【第11問】モチベーション理論(欲求段階説)
アブラハム・マズローの欲求5段階説において、最も高次な欲求とされるものはどれか。
A. 安全の欲求
B. 社会的欲求
C. 承認の欲求(尊厳欲求)
D. 自己実現の欲求
【第12問】リーダーシップ理論(条件適合理論)
部下の成熟度(能力・意欲)に応じて、リーダーは取るべきスタイルを変えるべきだとするリーダーシップ理論を何と呼ぶか。
A. PM理論
B. SL理論
C. パス・ゴール理論
D. オーセンティック・リーダーシップ
【第13問】パワーと影響力
ある人物が持つ公式な役職や地位に関係なく、その人の人柄や魅力、価値観への共感から生まれる影響力を何と呼ぶか。
A. カリスマ
B. フォロワーシップ
C. インフルエンサー
D. メンター
【第14問】チーム・マネジメントと役割
チーム内での役割に関する記述として、最も適切でないものを一つ選べ。
A. チームの目標達成に直接的に貢献する「タスク遂行役割」と、チームの人間関係を円滑にする「集団維持役割」がある。
B. 一人のメンバーが、複数の役割を同時に担うこともある。
C. チームのパフォーマンスを最大化するためには、全てのメンバーが同じ役割を担うべきである。
D. チームの発展段階に応じて、メンバーに求められる役割は変化することがある。
【第15問】コミュニケーションと障壁
コミュニケーションの過程で、送り手の意図が受け手に正しく伝わるのを妨げる要因(ノイズ)に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
A. 物理的ノイズ: 周囲の騒音や、オンライン会議での回線不良など。
B. 心理的ノイズ: 受け手の思い込みや偏見、感情的な状態など。
C. 意味的ノイズ: 送り手と受け手で、言葉の解釈が異なることによる誤解など。
D. フィードバック: 受け手がメッセージを理解したか確認する行為も、ノイズの一種である。
【第16問】変革への抵抗
組織変革を進める際に、従業員から抵抗が生まれる原因として、最も考えにくいものを一つ選べ。
A. 新しいやり方を学ぶことへの不安や、変化に伴う不利益への懸念。
B. これまでのやり方や成功体験への固執、慣れ親しんだ現状を維持したいという心理。
C. 変革の目的や必要性が、従業員に十分に理解・共感されていない。
D. 変革によって、自分の仕事がより楽になり、責任も軽くなると期待している。
【第17問】組織学習とイノベーション
既存の知識や成功体験が、かえって新しい環境への適応やイノベーションを阻害してしまう現象を何と呼ぶか。
A. イノベーションのジレンマ
B. コア・コンピタンス
C. サクセス・トラップ(成功の罠)
D. 学習する組織
【第18問】リーダーシップのスタイル
リーダーが明確なビジョンや変革の方向性を示し、部下の知的好奇心や高い理想に働きかけることで、期待以上の成果を引き出すリーダーシップ・スタイルを何と呼ぶか。
A. サーバント・リーダーシップ
B. 変革型リーダーシップ
C. オーセンティック・リーダーシップ
D. 支配型リーダーシップ
【第19問】モチベーション理論
外部からの報酬や罰ではなく、仕事そのものへの興味・関心や、達成感、成長実感といった、個人の内面から湧き上がる意欲を何と呼ぶか。
A. 外発的動機づけ
B. 内発的動機づけ
C. 衛生的動機づけ
D. 達成動機づけ
【第20問】パワーと影響
組織内において、公式な権限に基づかずに、非公式な人間関係や情報網を通じて他者に影響を及ぼそうとする行動を何と呼ぶか。
A. 組織内政治(ポリティクス)
B. コーポレート・ガバナンス
C. ネットワーク組織
D. コンプライアンス
【第21問】組織目標達成貢献
リーダーを主体的に支援し、時には建設的な批判を行うことで、組織の目標達成に貢献しようとする部下のあり方を何と呼ぶか。
A. リーダーシップ
B. メンバーシップ
C. フォロワーシップ
D. パートナーシップ
【第22問】公平理論
J.S.アダムスが提唱した公平理論に関する記述として、最も適切なものを一つ選べ。
A. 人は、自分の努力と報酬の絶対額だけで満足度を判断する。
B. 人は、自分自身の「インプット(努力・貢献)」と「アウトプット(報酬)」の比率を、他者の比率と比較し、不公平を感じるとそれを解消しようと動機づけられる。
C. 不公平を感じた場合、人は常により多くの報酬を要求する行動をとる。
D. この理論は、主に金銭的報酬に関するモチベーションを説明するものである。
【第23問】期待理論
V.H.ブルームが提唱した期待理論において、モチベーションは3つの要素の掛け算で決まるとされる。その3つの要素に含まれないものはどれか。
A. 期待: 努力すれば高い成果を上げられるだろうという期待の度合い。
B. 道具性(誘意性): 高い成果を上げれば、望ましい報酬が得られるだろうという期待の度合い。
C. 魅力: その報酬が、自分にとってどれだけ魅力的かという度合い。
D. 公平性: その報酬が、他者と比較して公平であるかという度合い。
【第24問】目標設定理論
E.A.ロックが提唱した目標設定理論に関する記述として、最もモチベーションを高めるとされる目標はどれか。
A. 「できるだけ頑張る」といった、曖昧で抽象的な目標。
B. 簡単に達成できる、非常に難易度の低い目標。
C. 達成が困難だが、努力すれば手が届く可能性のある、具体的で明確な目標。
D. 達成が不可能と思われる、極めて非現実的な目標。
【第25問】ジョブアプローチ
従業員が、自らに与えられた仕事の内容や人間関係、仕事に対する捉え方を、自律的に修正・再定義していくことで、仕事のやりがいを高めようとするアプローチを何と呼ぶか。
A. ジョブ・ローテーション
B. ジョブ・エンリッチメント
C. ジョブ・クラフティング
D. ジョブ・シェアリング
【第26問】組織市民行動(OCB)
従業員が、職務記述書で定められた公式な役割や義務ではないにもかかわらず、自発的に行う利他的で協力的な行動を何と呼ぶか。
A. 職務満足
B. 組織コミットメント
C. 組織市民行動
D. 職務怠慢
【第27問】リーダーシップのあり方
自分自身の価値観や信念に忠実であり、透明性のある言動で周囲との信頼関係を築くリーダーシップのあり方を何と呼ぶか。
A. サーバント・リーダーシップ
B. 変革型リーダーシップ
C. オーセンティック・リーダーシップ
D. カリスマ型リーダーシップ
【第28問】形式知
個人が持つ知識や経験といった「暗黙知」を、組織全体で共有・活用できる「形式知」へと変換・体系化していく経営手法を何と呼ぶか。
A. SECIモデル
B. ナレッジ・マネジメント
C. バリューチェーン
D. コア・コンピタンス
【第29問】経験学習モデル
D.A.コルブが提唱した、人が経験から学ぶプロセスを示した「経験学習モデル」のサイクルとして、正しい順番のものを選べ。
A. ①具体的経験 → ②内省的観察 → ③抽象的概念化 → ④能動的実験
B. ①内省的観察 → ②具体的経験 → ③能動的実験 → ④抽象的概念化
C. ①抽象的概念化 → ②能動的実験 → ③具体的経験 → ④内省的観察
D. ①能動的実験 → ②抽象的概念化 → ③内省的観察 → ④具体的経験
【第30問】リーダーシップ理論
リーダーは全ての部下と均一な関係を築くのではなく、一部の信頼する部下(イン・グループ)と、それ以外の部下(アウト・グループ)とで、異なる関係性を築くとするリーダーシップ理論は何か。
A. パス・ゴール理論
B. リーダー・メンバー交換(LMX)理論
C. SL理論
D. PM理論

お疲れ様でした!全30問、いかがでしたか?
これだけやりこめば合格は目の前です。間違えた問題は繰り返し解いて覚えていきましょう。
関連記事
他の科目はこちらから
















