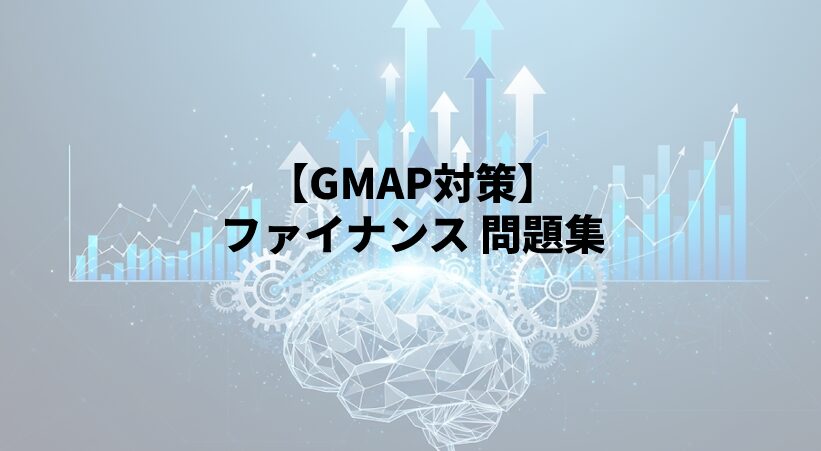
【第1問】企業経営と企業財務
企業財務(コーポレート・ファイナンス)の究極的な目標として、最も適切とされるものを一つ選べ。
A. 企業の売上高を最大化すること。
B. 従業員の満足度を最大化すること。
C. 企業の社会的貢献度を最大化すること。
D. 企業価値(株主価値)を最大化すること。
【第2問】ファイナンス理論の体系
現代ファイナンス理論の重要な前提の一つである「効率的市場仮説」に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
A. ウィーク・フォーム: 過去の株価の推移(テクニカル分析)を利用しても、超過リターンを得ることはできないとする考え方。
B. セミストロング・フォーム: 公開されている全ての情報(決算情報やニュースなど)を利用しても、超過リターンを得ることはできないとする考え方。
C. ストロング・フォーム: インサイダー情報を含む、全ての公開・非公開情報を利用しても、超過リターンを得ることはできないとする考え方。
D. 多くの実証研究により、現実の市場は常にストロング・フォームの効率性を満たしていることが確認されている。
【第3問】金銭の時間的価値:現在価値
金銭の時間的価値に関する記述として、最も適切なものを一つ選べ。
A. 将来受け取る100万円の価値と、現在保有している100万円の価値は、等しい。
B. 「現在価値」とは、将来受け取るキャッシュフローを、現在の価値に割り引いて評価したものである。
C. 割引率が高くなるほど、将来のキャッシュフローの現在価値は大きくなる。
D. 「複利」とは、元本に対してのみ利息が計算される方法である。
【第4問】DCF法 ※計算問題
ある投資案件が、1年後に110万円、2年後に121万円のキャッシュフローを生み出すと期待されている。割引率が年10%である場合、この投資案件が生み出すキャッシュフローの現在価値の合計はいくらになるか計算せよ。
A. 200万円
B. 210万円
C. 220万円
D. 231万円
【第5問】投資評価の様々な方法
投資の意思決定手法の一つである「IRR(内部収益率)法」に関する説明として、最も適切なものを一つ選べ。
A. 投資の回収期間の短さで、プロジェクトの優劣を判断する方法。
B. プロジェクトが生み出すキャッシュフローの現在価値の合計額を計算する方法。
C. 投資の正味現在価値(NPV)がゼロになる割引率を計算する方法。
D. 複数の投資プロジェクトを比較する際、常に正しい判断を下せる万能な手法である。
【第6問】分散投資の効果(1):ポートフォリオ理論
ポートフォリオ理論に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
A. 複数の資産に分散投資を行うことで、個別の資産が持つリスクを低減させる効果がある。
B. ポートフォリオ全体のリスクは、組み入れた各資産のリスクを単純に加重平均したものと等しくなる。
C. 異なる値動きをする資産(相関が低い資産)を組み合わせるほど、リスク低減効果は大きくなる。
D. ポートフォリオ全体の期待リターンは、組み入れた各資産の期待リターンを加重平均したものとなる。
【第7問】分散投資の効果(2):効率的フロンティア
ポートフォリオ理論における「効率的フロンティア」に関する説明として、最も適切なものを一つ選べ。
A. 全ての投資家が目標とすべき、単一の最適なポートフォリオのこと。
B. リスクを全く取らない、安全資産のみで構成されたポートフォリオのこと。
C. 同じリスク水準であれば、最も高い期待リターンが得られるポートフォリオの集合を結んだ線のこと。
D. 分散投資を行っても、決して低減できない市場全体のリスクのこと。
【第8問】分散投資の効果(3):CAPM ※計算問題
以下の条件のとき、CAPM(資本資産価格モデル)を用いて算出される株式Aの期待リターンは何%になるか計算せよ。
- リスクフリーレート(長期国債利回り): 1%
- マーケット全体の期待リターン(TOPIXなど): 6%
- 株式Aのβ(ベータ)値: 1.2
A. 6.0%
B. 7.0%
C. 7.2%
D. 8.2%
【第9問】企業の資金調達手段
企業の資金調達方法である「直接金融」と「間接金融」に関する記述として、正しいものを一つ選べ。
A. 銀行からの借入は、企業が市場の投資家から直接資金を調達するため、「直接金融」に分類される。
B. 株式や社債の発行は、金融機関を介さずに投資家から直接資金を調達するため、「直接金融」に分類される。
C. 間接金融は、直接金融に比べて、企業の機密情報が市場に広く開示されるというデメリットがある。
D. ベンチャー企業などの新興企業は、信用力が低いため、間接金融よりも直接金融の方が資金調達しやすい。
【第10問】資本コスト ※計算問題(WACC)
以下の情報に基づき、この企業のWACC(加重平均資本コスト)は何%になるか計算せよ。
- 有利子負債額 (D): 400億円
- 株主資本時価総額 (E): 600億円
- 負債コスト (rD): 2%
- 株主資本コスト (rE): 7%
- 実効法人税率 (t): 30%
A. 3.84%
B. 4.76%
C. 5.00%
D. 9.00%
【第11問】株主資本コストの推定
株主資本コストを推定する際に用いられるCAPMの構成要素である「β(ベータ)値」に関する説明として、最も適切なものを一つ選べ。
A. 個別株式のリターンの、市場全体のリターンに対する感応度を示す指標である。
B. β値が1より大きい株式は、市場全体よりも値動きが小さい「ディフェンシブ銘柄」とされる。
C. β値が1の株式は、市場全体と全く相関なく動くことを意味する。
D. β値がマイナスになることは、理論上あり得ない。
【第12問】市場の効率性
ファイナンス理論における「効率的な市場」とは、どのような状態を指すか。最も適切なものを一つ選べ。
A. 全ての投資家が、常に利益を上げられる市場。
B. 株価の変動が全くなく、安定している市場。
C. 新しい情報が、瞬時に、かつ正確に資産価格に反映される市場。
D. 政府の規制によって、株価が厳格に管理されている市場。
【第13問】企業の最適資本構成(1):理論
モジリアニ=ミラー(MM)理論に関する記述として、法人税が存在しない完全市場を前提とした場合、正しいものを一つ選べ。
A. 企業の資金調達方法(負債と株主資本の比率)は、企業価値に影響を与える。
B. 負債比率を高めるほど、支払利息の節税効果により、企業価値は高まる。
C. 企業価値は、その企業がどのような資産(事業)に投資しているかによって決まり、資金調達方法には依存しない。
D. 最適な資本構成が存在し、それを達成することで企業価値を最大化できる。
【第14問】企業の最適資本構成(2):実際
現実の世界で企業の最適資本構成を考える際に、負債を増やすことのデメリット(コスト)として、最も代表的なものを一つ選べ。
A. 支払利息の節税効果
B. 財務レバレッジ効果
C. 倒産リスクの増大(財務的困難性のコスト)
D. 株主への配当金の減少
【第15問】配当政策
企業の配当政策に関する記述として、最も適切なものを一つ選べ。
A. MM理論によれば、完全市場のもとでは、配当政策は企業価値に影響を与えない(配当無関連性命題)。
B. 企業が内部留保を増やして配当を減らすことは、常に株主にとって不利益となる。
C. 安定配当政策は、企業の将来の成長性に対する、経営者のネガティブなシグナルとして市場に受け取られる。
D. 株主は、配当によるインカムゲインよりも、株価上昇によるキャピタルゲインの方を常に好む。
【第16問】フリー・キャッシュフロー ※計算問題
以下の情報に基づき、この企業のフリー・キャッシュフロー(FCF)はいくらになるか計算せよ。
- EBIT(税引前営業利益): 500万円
- 法人税率: 30%
- 減価償却費: 100万円
- 設備投資額: 80万円
- 運転資本増加額 (ΔWC): 50万円
A. 220万円
B. 320万円
C. 420万円
D. 520万円
【第17問】企業価値の算出
企業価値評価(バリュエーション)に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
A. 企業価値は、一般的に「事業価値」と「非事業資産価値」の合計として算出される。
B. DCF法で算出される事業価値は、将来のフリー・キャッシュフロー(FCF)をWACCで現在価値に割り引くことで求められる。
C. 「株主価値」は、「企業価値」から「有利子負債」の価値を差し引くことで算出される。
D. 企業価値と株式時価総額は、常に一致する。
【第18問】株式評価モデル
株式の価値を評価する配当割引モデル(DDM)に関する記述として、最も適切なものを一つ選べ。
A. 企業の資産価値に基づいて、株価を評価するモデルである。
B. 株価は、その株式を保有することで将来得られる配当の現在価値の合計に等しいと考える。
C. 配当を全く支払っていない、成長段階にある企業の株価評価に適している。
D. このモデルでは、金銭の時間的価値は考慮されない。
【第19問】EVA(経済的付加価値)
EVA (Economic Value Added) に関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
A. EVAは、企業が資本コストを上回って、どれだけの経済的価値を創造したかを示す指標である。
B. EVAの計算式は、「税引後営業利益(NOPAT) - (投下資本 × WACC)」で表される。
C. EVAがプラスであれば、企業は株主や債権者の期待リターン(資本コスト)を上回る価値を生み出していると評価できる。
D. EVAは、会計上の利益である当期純利益と、常に同じ値になる。
【第20問】オプション理論の基礎
オプション取引における「コールオプション」とは、どのような権利か。
A. 原資産を、将来の特定の期日に、特定の価格で売る権利。
B. 原資産を、将来の特定の期日に、特定の価格で買う権利。
C. 原資産を、将来の特定の期日に、特定の価格で売る義務。
D. 原資産を、将来の特定の期日に、特定の価格で買う義務。
【第21問】企業買収防衛策
敵対的買収に対する防衛策の一つである「ポイズンピル(毒薬条項)」に関する説明として、最も適切なものを一つ選べ。
A. 買収者以外の既存株主に対して、新株を市場価格よりも安く購入できる権利(新株予約権)をあらかじめ付与しておく手法。
B. 会社の資産の中で、特に魅力的な事業や資産(クラウン・ジュエル)を第三者に売却してしまう手法。
C. 友好的な第三者(ホワイトナイト)に、買収者よりも有利な条件で自社を買収してもらう手法。
D. 役員の退職金を高額に設定し、買収後の経営陣交代のコストを高くする手法。
【第22問】投資ファンド
様々な投資家から集めた資金を、専門家が株式や債券などに投資・運用する仕組みを何と呼ぶか。
A. ヘッジファンド
B. ベンチャーキャピタル
C. 投資信託
D. プライベート・エクイティ・ファンド
【第23問】金融オプション理論
不確実性の高い投資プロジェクトについて、将来の状況変化に応じて計画を柔軟に修正(延期、拡大、縮小、撤退など)できる権利を、金融のオプション理論を応用して評価する考え方を何と呼ぶか。
A. ペイバック法
B. IRR法
C. リアルオプション
D. EVA
【第24問】LBO(レバレッジド・バイアウト)
M&Aの手法の一つであるLBOに関する記述として、最も適切なものを一つ選べ。
A. 買収先の企業の資産や将来のキャッシュフローを担保に、金融機関から多額の資金を調達して企業を買収する手法。
B. 複数の企業が共同で、一つの企業を買収する手法。
C. 経営陣が、自社の株式を株主から買い集めて非公開化する手法。
D. 友好的な第三者と協力して、敵対的買収者に対抗する手法。
【第25問】プロジェクト・ファイナンス
特定のプロジェクト(例:大規模インフラ開発)の資産や将来生み出すキャッシュフローのみを返済原資として、資金調達を行う金融手法を何と呼ぶか。
A. コーポレート・ファイナンス
B. プロジェクト・ファイナンス
C. アセット・ファイナンス
D. トレード・ファイナンス
【第26問】債券の価格と金利の関係
債券の市場価格と市場金利の関係に関する記述として、正しいものを一つ選べ。
A. 市場金利が上昇すると、既に発行されている固定利付債券の価格は上昇する。
B. 市場金利が下落すると、既に発行されている固定利付債券の価格は上昇する。
C. 市場金利の変動は、債券の価格に影響を与えない。
D. 債券の残存期間が短いほど、金利変動に対する価格の感応度は高くなる。
【第27問】株主還元の方法
企業が株主に利益を還元する方法として、配当金の支払い以外に代表的なものは何か。
A. 役員報酬の増額
B. 従業員への賞与の支給
C. 自社株買い
D. 設備投資の拡大
【第28問】行動ファイナンス
人々が必ずしも合理的に行動するとは限らないという、心理学の知見をファイナンス理論に取り入れた学問分野を何と呼ぶか。
A. コーポレート・ファイナンス
B. 行動ファイナンス
C. 数理ファイナンス
D. 公共ファイナンス
【第29問】財務レバレッジ
財務レバレッジに関する記述として、誤っているものを一つ選べ。
A. 他人資本(負債)を利用することで、自己資本利益率(ROE)を高める効果のこと。
B. 事業で得られる利益率(ROA)が、負債の利子率を上回っている場合に、プラスのレバレッジ効果が働く。
C. 負債比率を高めるほど、レバレッジ効果によりROEは無限に高まっていく。
D. 業績が悪化してROAが利子率を下回ると、逆にROEを押し下げる「負のレバレッジ」が働くリスクがある。
【第30問】永続価値
DCF法で企業価値を算出する際に、予測期間よりも先の期間について、事業が永続的に生み出すと仮定されるキャッシュフローの現在価値を何と呼ぶか。
A. NPV(正味現在価値)
B. IRR(内部収益率)
C. ターミナルバリュー
D. EVA(経済的付加価値)

お疲れ様でした!全30問、いかがでしたか?
これだけやりこめば合格は目の前です。間違えた問題は繰り返し解いて覚えていきましょう。
関連記事
他の科目はこちらから















