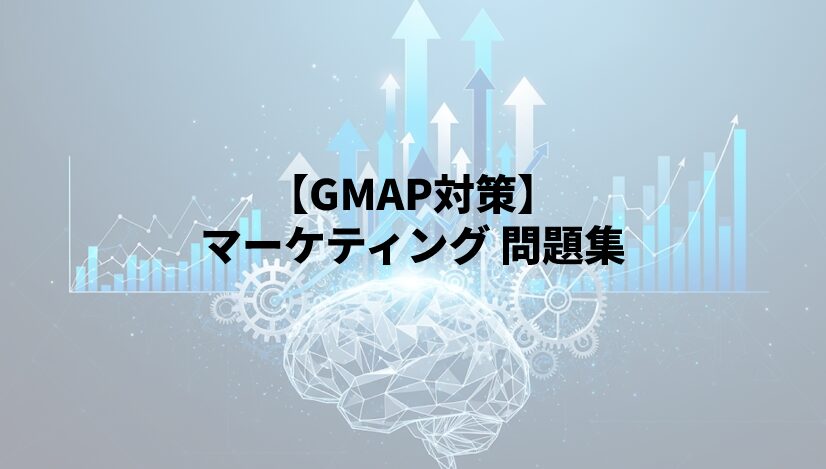
1.マーケティングの発想
■問1. マーケティングの基本的な考え方について、以下の記述の中から、誤っているものをすべて選択してください。
A. マーケティングは、顧客満足を起点として「売れ続ける仕組み」を構築する活動であり、その範囲は広告や営業活動に限定されない。
B. セリング(販売)は、作り手側の論理で「いかに売るか」を考える短期志向の活動である。
C. マーケティングは、買い手側の論理で「いかに買ってもらうか」を考えるため、中長期的な視点が求められる。
D. 優れた製品さえ開発すれば、マーケティング活動を行わなくても、製品は自然と売れていくものである。
2.マーケティングの役割
■問2. マーケティングが企業経営において果たす役割について、正しいものを一つ選択してください。
A. 企業の役割は、自社の技術シーズを基に画期的な製品を生み出すことであり、マーケティングはそれに付随する活動である。
B. マーケティング戦略は、主に製品開発部門が担うべき専門的な戦略である。
C. ポーターが提唱した「コスト・リーダーシップ戦略」「差別化戦略」「集中戦略」は、マーケティング戦略の代表的なフレームワークである。
D. 市場環境の変化を捉え、顧客の期待を明確化し、企業の進むべき方向性を経営戦略に統合していく役割を担う。
3. マーケティング・マネジメ
■問3. マーケティング戦略の立案プロセスに関する下記文章中の(①)~(④)に入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを選択してください。
マーケティング戦略の立案は、一般的に環境分析から始まる。次に、市場を共通のニーズで分類する( ① )を行い、その中から自社が狙うべき市場を選定する( ② )へと進む。そして、競合製品との違いを明確にし、顧客の心の中に独自の価値を位置づける( ③ )を行う。最後に、これらの戦略を具体的な戦術に落とし込む( ④ )を設計する。
A. ①ターゲティング ②ポジショニング ③セグメンテーション ④マーケティング・リサーチ
B. ①セグメンテーション ②ターゲティング ③ポジショニング ④マーケティング・ミックス
C. ①ポジショニング ②セグメンテーション ③ターゲティング ④SWOT分析
D. ①マーケティング・リサーチ ②SWOT分析 ③セグメンテーション ④ターゲティング
4.市場の機会の発見
■問4. 市場機会の発見やSWOT分析に関する記述として、誤っているものを一つ選択してください。
A. SWOT分析とは、企業の内部環境である「強み」「弱み」と、外部環境である「機会」「脅威」を分析するフレームワークである。
B. 自社ではコントロールが困難な法改正や景気変動などは、外部環境の分析対象となる。
C. 一見すると「脅威」に見える環境変化も、視点を変えたり自社の「強み」と掛け合わせたりすることで、「機会」に転換できる可能性がある。
D. SWOT分析で洗い出した4つの要素のうち、最も優先して取り組むべきは「弱み」の克服である。
5.マーケティング・リサーチ
■問5. マーケティング・リサーチのプロセスに関する記述として、正しい順番に並んでいるものを一つ選択してください。
A. ①仮説の設定 → ②リサーチ目的の設定 → ③リサーチの設計と実施 → ④データの分析と仮説検証
B. ①リサーチ目的の設定 → ②仮説の設定 → ③リサーチの設計と実施 → ④データの分析と仮説検証
C. ①リサーチの設計と実施 → ②リサーチ目的の設定 → ③仮説の設定 → ④データの分析と仮説検証
D. ①データの分析と仮説検証 → ②仮説の設定 → ③リサーチ目的の設定 → ④リサーチの設計と実施
6. セグメンテーションとター
■問6. 市場を細分化(セグメンテーション)する際の基準(変数)に関する記述として、適切でないものを一つ選択してください。
A. 年齢、性別、職業、所得といった客観的な基準は「人口動態変数(デモグラフィック変数)」と呼ばれる。
B. ライフスタイルや価値観、パーソナリティといった心理的な基準は「心理的変数(サイコグラフィック変数)」と呼ばれる。
C. 製品の使用頻度や求めるベネフィット(便益)といった顧客の行動に着目した基準は「行動変数」と呼ばれる。
D. 企業の売上規模や業種、従業員数といった基準は、BtoCマーケティングにおける主要なセグメンテーション変数である。
7. ポジショニング
■問7. ポジショニング戦略に関する記述として、最も適切なものを一つ選択してください。
A. ポジショニングとは、物理的に最も良い立地の店舗を確保することである。
B. 競合製品がひしめく市場の中心に自社製品を位置づけることで、最大の売上を目指す戦略である。
C. 顧客の頭の中に、競合製品と比較して自社製品が持つ独自の価値や魅力を明確に位置づけるための活動である。
D. 製品の価格を市場で最も安く設定し、価格リーダーとしての地位を確立することである。
8. 製品特性
■問8. 製品を構成する3つのレベル(中核、実体、付随機能)に関する記述として、誤っているものを一つ選択してください。
A. 「製品の中核」とは、顧客がその製品に求める基本的な便益(ベネフィット)や機能価値のことである。
B. 「製品の実体」とは、中核となる価値を具現化したもので、品質、デザイン、ブランド名などが含まれる。
C. 「製品の付随機能」とは、製品価値を高める追加的なサービスや便益のことで、保証やアフターサービスがこれにあたる。
D. 競合製品との差別化を図るためには、「製品の中核」レベルでの競争が最も重要となる。
9. ブランド
■問9. ブランドが持つ機能に関する記述として、当てはまらないものを一つ選択してください。
A. 出所表示機能: その製品が誰によって作られたかを示す機能。
B. 品質保証機能: あのブランドだから品質は間違いないだろう、と顧客に安心感を与える機能。
C. 価値意味づけ機能: そのブランドを持つことで、顧客に自己表現や満足感といった感情的な価値を提供する機能。
D. 原価低減機能: ブランド力を高めることで、製品の製造原価を直接的に引き下げる機能。
10. 新製品開発
■問10. 新製品開発のプロセスに関する記述として、最も適切なものを一つ選択してください。
A. 優れたアイデアをできるだけ多く実現させるため、アイデアの絞り込み(スクリーニング)は行うべきではない。
B. 製品コンセプトが固まった後、市場に投入する前に、その製品が事業として成立するかどうかを評価する「事業性分析」が行われる。
C. 市場テストは、開発コストを抑えるために、製品が完成してからではなく、コンセプト段階で行うのが一般的である。
D. 新製品開発は、一度市場に投入(上市)したら完了であり、その後の評価や改善は不要である。
11. 製品ライフサイクル
■問11. 「製品ライフサイクル」の各段階における特徴とマーケティング戦略の組み合わせとして、最も適切でないものを一つ選択してください。
A. 導入期: 製品の認知度が低いため、認知度向上を目的としたプロモーションに注力する。
B. 成長期: 市場が急拡大し競合も参入してくるため、市場シェアの最大化を目指す。
C. 成熟期: 市場の成長が鈍化し競争が激化するため、競合との差別化や顧客の囲い込みが重要になる。
D. 衰退期: 売上・利益が減少し始めるため、さらなる大規模な投資を行い、市場を再活性化させる。
12. 価値と事業経済性
■問12. 顧客が感じる価値(カスタマーバリュー)に関する記述として、最も適切なものを一つ選択してください。
A. 顧客価値とは、製品の販売価格そのものを指す。
B. 顧客価値は、顧客が製品やサービスから得られる便益(ベネフィット)から、その獲得にかかるコスト(金銭的・時間的・心理的コスト)を差し引いたものである。
C. 全ての顧客は、製品に対して同じ価値を感じるため、マーケティングは画一的に行うべきである。
D. 顧客価値を高める唯一の方法は、製品の価格を下げることである。
13. 戦略的価格設定
■問13. 製品の価格設定アプローチに関する文章の( )に入る語句として、正しいものを下記語群から選び、記号で回答ください。
コストを基準にするコスト志向アプローチには、かかった費用に一定の利益を上乗せする( ① )法がある。一方、顧客が製品に感じる価値を基準にするアプローチには( ② )価格設定がある。また、競合他社の価格を基準にするアプローチには( ③ )価格決定方式がある。
【語群】
A:マークアップ
B:知覚価値
C:実勢
【解答選択肢】
①C → ②A → ③B
①A → ②B → ③C
①B → ②C → ③A
14. 流通チャネルの意義
■問14. メーカーが卸売業者や小売業者といった流通チャネルを活用する意義として、誤っているものを一つ選択してください。
A. 自社ですべての顧客に直接販売するリソースがない場合でも、効率的に製品を市場に届けることができる。
B. 各地域の販売や在庫管理、代金回収などを専門業者に任せることで、自社は製品開発やマーケティングに集中できる。
C. 顧客との直接的な接点が減るため、顧客からのフィードバックや市場の変化を捉えにくくなるというデメリットもある。
D. 流通業者を介することで、製品価格やブランドイメージのコントロールが、直販の場合よりも容易になる。
15. 流通チャネルの構築プロ
■問15. 流通チャネルの「開放度」に関する戦略の組み合わせとして、最も適切なものを一つ選択してください。
A. 開放的チャネル政策: 限定された地域で、特定の業者に独占販売権を与える。
B. 選択的チャネル政策: ブランドイメージを維持するため、一定の基準を満たした業者にのみ製品を取り扱わせる。
C. 排他的(専属的)チャネル政策: できるだけ多くの業者に製品を取り扱ってもらい、顧客がどこでも購入できるようにする。
16. コミュニケーション手段
■問16. プッシュ戦略とプル戦略に関する記述として、正しいものを一つ選択してください。
A. プッシュ戦略とは、消費者に直接広告を打ち、消費者が小売店に商品を指名買いするよう仕向ける戦略である。
B. プル戦略とは、メーカーが卸売業者や小売業者に対し、リベート(販売奨励金)などのインセンティブを提供して販売を促進する戦略である。
C. プッシュ戦略とプル戦略は、どちらか一方を選択して実行するべきであり、併用することはできない。
D. 一般的に、テレビCMなどで消費者の購買意欲を喚起するのがプル戦略、営業担当者が小売店に自社製品の陳列を働きかけるのがプッシュ戦略である。
17. 広告戦略
■問17. 広告戦略を構成する二つの要素に関する記述として、正しいものを一つ選択してください。
A. 「メディア戦略」とは、広告で伝えるべきメッセージの内容や表現方法を決定することである。
B. 「クリエイティブ戦略」とは、どの媒体(テレビ、Web、雑誌など)に広告を掲載するかを決定することである。
C. 広告戦略の第一歩は、ターゲット顧客を定めず、できるだけ多くの人にメッセージを伝えることである。
D. 「誰に(ターゲット)」「何を(メッセージ)」「どのように(表現)」「どこで(媒体)」を統合的に設計することが重要である。
18. セールス・プロモーショ
■問18. セールス・プロモーション(SP)に関する記述として、最も適切なものを一つ選択してください。
A. ブランドイメージの構築を目的とした、中長期的なコミュニケーション活動である。
B. クーポン、サンプリング、増量パックなど、消費者の短期的な購買を直接的に刺激するための活動である。
C. 主に、テレビCMや新聞広告といったマスメディアを通じて行われる。
D. 広告とセールス・プロモーションは、目的が同じであるため、どちらか一方を行えばよい。
19. 顧客維持型マーケティン
■問19. 新規顧客の獲得よりも、既存顧客との関係維持を重視するマーケティングに関する記述として、誤っているものを一つ選択してください。
A. 新規顧客を獲得するコストは、一般的に既存顧客を維持するコストよりも高いと言われている。
B. 顧客ロイヤルティが高い顧客は、購買頻度が高いだけでなく、口コミによる新規顧客の紹介も期待できる。
C. ITの進化により、顧客一人ひとりの情報を管理し、パーソナライズされたコミュニケーションを行うことが容易になった。
D. 顧客維持型マーケティングは、すべての業種・製品において、新規顧客獲得よりも常に優先されるべき戦略である。
20. BtoBマーケティング
■問20. BtoB(法人向け)マーケティングの特徴として、BtoC(消費者向け)マーケティングと比較した場合、適切でないものを一つ選択してください。
A. 購買の意思決定に、複数の部署や役職者が関与することが多い。
B. 製品・サービスの選定において、機能、価格、サポート体制といった合理的な判断基準が重視される傾向がある。
C. 顧客数は比較的少ないが、一顧客あたりの取引額が大きくなる傾向がある。
D. 衝動買いや感情的な要因が購買を決定づけることが大半である。
21. レピュテーション
■問21. 企業のレピュテーション(評判)マネジメントに関する記述として、最も適切なものを一つ選択してください。
A. レピュテーションはブランドイメージとほぼ同義であり、マーケティング活動とは直接関係がない。
B. 良いレピュテーションは、顧客の購買意欲や従業員のエンゲージメントを高めるなど、企業の無形資産となる。
C. 現代では、悪いレピュテーションよりも良いレピュテーションの方が、SNSなどを通じて拡散しやすい。
D. レピュテーションは自然に形成されるものであり、企業がコントロールすることは不可能である。
22. プロダクト・ポートフォ
■問22. PPM(ボストン・コンサルティング・グループ提唱)で用いられる4つの象限に関する記述として、誤っているものを一つ選択してください。
A. 花形(Star): 市場成長率・相対的市場シェアがともに高く、将来の「金のなる木」とするために積極的な投資が必要。
B. 金のなる木(Cash Cow): 市場成長率は低いがシェアは高く、安定的にキャッシュを生み出す事業。
C. 問題児(Question Mark): 市場成長率は高いがシェアは低く、将来性を見極めて投資を強化するか撤退するか判断が必要。
D. 負け犬(Dog): 市場成長率・シェアがともに低く、事業が生み出すキャッシュが最も大きい。
23. ブランド・エクイティ
■問23. ブランド・エクイティ(ブランドが持つ資産価値)の構成要素に関する記述の組み合わせとして、正しいものを一つ選択してください。
A. ブランド認知: そのブランドがどれだけ知られているか。
B. 知覚品質: そのブランドの実際の製造原価。
C. ブランドロイヤルティ: そのブランドの広告宣伝費の総額。
D. ブランド連想: そのブランドの従業員数。
24. トリプルメディア
■問24. 企業が利用するメディアを3つに分類した「トリプルメディア」の組み合わせとして、適切なものを下記から選んでください。
企業が自ら所有し、コントロールできるメディアを( ① )、費用を払って広告を掲載するメディアを( ② )、そして顧客や第三者による口コミや評判が掲載されるメディアを( ③ )と呼ぶ。
A. ①アーンドメディア ②オウンドメディア ③ペイドメディア
B. ①ペイドメディア ②アーンドメディア ③オウンドメディア
C. ①オウンドメディア ②ペイドメディア ③アーンドメディア
25. 現代の購買行動モデル
■問25. フィリップ・コトラーが提唱した、現代の顧客の購買行動プロセス「5Aモデル」の正しい順番を選んでください。
A. 認知(Aware) → 訴求(Appeal) → 調査(Ask) → 行動(Act) → 推奨(Advocate)
B. 認知(Aware) → 調査(Ask) → 訴求(Appeal) → 行動(Act) → 推奨(Advocate)
C. 訴求(Appeal) → 認知(Aware) → 調査(Ask) → 行動(Act) → 推奨(Advocate)
26. コンテンツマーケティン
■問26. コンテンツマーケティングに関する記述として、最も本質を捉えているものを一つ選択してください。
A. 自社製品の割引情報やセールスポイントのみを、ブログやSNSで継続的に発信すること。
B. 競合他社の人気コンテンツをコピーし、自社サイトのページ数を増やすこと。
C. 見込み顧客にとって価値のある、役立つ情報を提供し続けることで信頼関係を築き、最終的にファンになってもらうことを目指す活動。
D. 短期間でWebサイトへのアクセス数を急増させることを唯一の目的とする活動。
27. SEO(検索エンジン最
■問27. SEOに関する記述として、現代の考え方として誤っているものを一つ選択してください。
A. ユーザーの検索意図を深く理解し、その問いに最も的確に答える質の高いコンテンツを作成することが重要である。
B. Googleからペナルティを受けるリスクがあるため、作為的に大量の被リンクを購入するなどのブラックハットSEOは避けるべきである。
C. サイトの表示速度を改善したり、スマートフォンでの見やすさを確保したりすることも、SEOの評価要因に含まれる。
D. 検索順位を上げるためには、コンテンツの内容よりも、キーワードを可能な限り多くページ内に詰め込むことが最も効果的である。
28. SNSマーケティング
■問28. 企業のSNSマーケティングにおけるKPI(重要業績評価指標)の設定に関する記述として、最も適切なものを一つ選択してください。
A. どのような目的のキャンペーンであっても、KPIは常に「フォロワー数」に設定すべきである。
B. キャンペーンの目的が「認知度拡大」の場合、「エンゲージメント率」や「インプレッション数」をKPIとするのが適切である。
C. キャンペーンの目的が「ECサイトでの売上向上」の場合、「投稿のいいね!数」をKPIとするのが最も適切である。
D. KPIは一度設定したら、キャンペーンの結果に関わらず変更するべきではない。
29. CRM(顧客関係管理)
■問29. CRM(Customer Relationship Management)の主な目的として、最も適切なものを一つ選択してください。
A. 競合他社の顧客リストを不正に入手し、自社の営業活動に利用すること。
B. クレーム対応のプロセスを複雑化し、コストを削減すること。
C. 顧客情報を一元管理・分析し、個々の顧客に合わせたアプローチを行うことで、LTV(顧客生涯価値)を最大化すること。
D. 新規顧客の獲得のみに特化し、マーケティング活動を効率化すること。
30. NPS®
■問30. 顧客ロイヤルティを測る指標、NPS®に関する記述として、正しいものを一つ選択してください。
A. 「この製品に満足していますか?」という質問で、顧客満足度を測る指標である。
B. 「推奨者」の割合から「中立者」の割合を引いて算出される。
C. NPS®のスコアは、企業の将来的な収益成長率と相関が高いとされている。
D. スコアは0から100の範囲で示され、マイナスになることはない。

お疲れ様でした!全30問、いかがでしたか?
これだけやりこめば合格は目の前です。間違えた問題は繰り返し解いて覚えていきましょう。
関連記事
他の科目はこちらから
















